
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
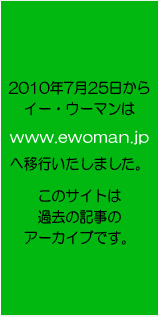 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子どもたちの科学する心を養いたい
「かがっきーず」という子ども向けの科学サイトを制作運営していますが、毎日たくさんの質問が寄せられます。男の子、女の子に関わらず、地球や宇宙のこと、からだのこと、動物や植物のこと。自分たちに関わりのあるすべてのことが、興味の対象になっていることがわかります。 興味を覚えたら、次に大事なのは、調べる、あるいは考えること。子どもが小さいうちは、一番身近な存在である親に、「これは何?」「どうして?」と聞いてくるでしょう。 そのとき、突き放したりごまかしたりしないで、いっしょに考えたり、調べてみたりすることで、子どもの科学的な探究心が養われるだけでなく、親子の会話によるコミュニケーションが図れるのですから、こんないいことはありません。 以前、国立の研究所の優秀な若手の研究者10人を取材したことがあります。9名の父親が研究者・技術者もしくは理科系の出身で、1名は農家。そして、全員が、自分の進路選択に、親の影響が大きかったことを述べていました。理科系センスの遺伝もあるかもしれませんが、それ以上に、科学的な環境によるものが大きかったように感じられたのです。 先日もお話ししたとおり、わたしは文系人間ですが、自分の娘には科学的な人間になって欲しいと思い、仕事の合間にできるだけ科学館を行脚し、また山を散策したり、星を観に行ったりしました。娘が高校で理系に進んだのはその成果かな、と思いますが、逆に文系科目が苦手になってしまいました。なかなか思うようにはいかないものですね(苦笑)。 子どもたちの科学離れが叫ばれています。日本全体でみると、理科の知識の希薄さが増しているのは、マスコミなどで言われている通りだと思います。 しかし、一方で科学は飛躍的に進歩していますし、こと「女性」において考えると、女性と科学は、ずいぶん身近になったのではないでしょうか。 科学の知識もさることながら、科学的思考能力があらゆるシーンで求められているように思います。世界中が混沌とし、人々の心が病みがちなこの時代。科学とは、真実を追求することではないかと、わたしは認識します。 わたしたちの子どもたち、そのまた子どもたちが幸せに暮らせるように。科学する心を養いたいと、みなさんのすてきな意見を読みながら思いました。 | 
コスモピア代表取締役 |
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |