
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
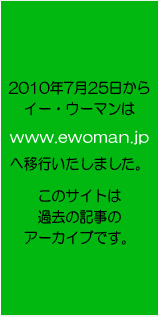 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判員制度は司法への信頼醸成策ゆりぼたるさん、わたしの友人も、ゼミの教授から言われたことを思い出していましたよ。「日本では、隣の八百屋の親父に裁かれるならば、頭のいい裁判官に裁かれたいという意識が根強い」と。日本では、専門家を敬う考え方で、きた。権威化して遠ざける行動パターンが、今まで日本の秩序・治安維持に連なり、他方で長いものに巻かれろ式の自発性のなさになっていたのですね。 アメリカでは、そもそも開拓時代に町に専門家はいないから任せられないし、みんなが自発的に物事を決めざるを得なかった。立法・行政も、司法も、みんながその役をこなしたわけです。そして、偉大な一般人、つまりコモンセンスこそ大概において間違いがないという考え方で、きた。陪審制によく表れていますね。 では、日本で今、なぜ、陪審類似の「裁判員」が登場するのか。司法改革会議などでは、個々の被告人のためというよりも、社会が司法に対する信頼をより厚くするため、と説明されています。規制緩和の大きな社会の流れの中で、紛争は増えますが、事前規制ではなく、事後処理へ回されます。そこで、司法への信頼醸成策ということです。まさになべさんの言われるところです。拡大解釈すると、国民の自発性(自分で見て考え意見表明し責任ある判断をする)を教育するという意味まであるのかも。 エコさんが言うように、裁判員は、専門家の長所と市民の長所を合わせたものになると良いですね。人数をどうするかは決まっていないようですが、市民のほうを多くする案が有力です。権限は、裁判官も裁判員も各人平等を考えているようです。画期的ですね。裁判員は、あちこちのオフィスから選任されるほど多くはないでしょうが、それでも企業にとっては裁判員として送り出す義務があるわけです。ワークシェアの一つのインパクトになったらおもしろいですね(なお、日当・交通費は裁判所から出る予定です。また、選挙人名簿から無作為抽出で選任されますが、25歳以上または30歳以上にする予定のようです)。 なお、日弁連が制作を依頼した、映画『裁判員 決めるのはあなた』が、大好評にて、巡回上映中だそうです。石坂浩二さん、岩崎ひろみさんらが出演しており、検察官も涙をぬぐう出来栄えだそうです。森山法務大臣は、全国の検察官に「これを観よ」との指令を出したそうです。機会があれば観てみると裁判員制度の理解の一端となるかもしれませんね。 | 
弁護士 |
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を!![]() 詳細と登録
詳細と登録
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |