
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
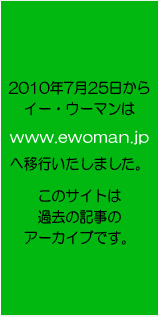 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一人ひとりがバランスを持った考えを「対話」か「圧力」か、最終的にほぼ半々という結果ですが、結局、いずれがいいのかについての結論は出なかったと言っていいでしょう。しかし、これは、逆に、「対話」も「圧力」も両方とも必要である、という結論が出たことを意味しているといえる結果なのかもしれません。実際、多くの指摘があったように、「対話」のみでは、なかなか北朝鮮が姿勢を変化しないし、一方で「圧力」に偏れば北朝鮮の反応がどのようなものになるのか不透明であるのも事実です。そうであるとすれば、わたしたちは、「対話」と「圧力」の両方を用いて粘り強く北朝鮮に臨んでいくしかないのかもしれません。それこそが「外交手腕」ということになるのでしょう。 「対話」と「圧力」いずれも必要ですが、その際、大前提になるのが国際的協調体制です。ただ、この国際的協調体制とは、なにも、日本、米国、韓国、さらには中国、ロシアがまったく同じ政策をとらなければならない、ということを意味するわけではありません。関係国はそれぞれ北朝鮮に求めるものに違いがあるのは事実です。 たとえば、日本にとっては、国際社会が問題としている北朝鮮の大量破壊兵器問題のみならず拉致問題、工作船問題など、さまざまな日朝固有の問題があります。また、韓国にとっては、統一問題、離散家族問題など、ここにもまた、さまざまな固有の問題があります。さらに中国にとっては、周辺地域の安定の問題、また脱北者問題など、やはり固有の問題があるのです。もちろん、より広い意味で考えれば、それぞれが固有に抱える問題というのはかならずしも別の国に関係がないというわけではありませんが、その優先順位が違うのは当然のことですし、それぞれの国の北朝鮮に対する政策に違いがあるのは当たり前のことです。ただ、重要なのは、その際、ある国の政策が、ほかの国の政策の妨げになっては意味がありません。 それゆえ、重要なのは、日本、米国、韓国、さらには中国、ロシアも含めて、国際社会としての最優先の目標を定め、それぞれが固有に抱える問題を把握し、自国の政策が他国の目標達成の妨げにならないような国際的な協力体制を作らなければならないのです。そうした体制の中で、それぞれ固有に抱える問題を解決していかなければならないのです。 もちろん、これがきわめて難しいことであるというのは事実です。しかし、北朝鮮問題についての最低限の「国際社会の目標」を設定しなければ、関係国それぞれの北朝鮮に対する姿勢が定まらないことは言うまでもないし、国際社会が北朝鮮に求めていることについて間違ったメッセージを与えてしまいます。実は、対話と圧力をうまく使い分けるためには、関係国間の調整がまずもって必要とされるのです。 そして、関係国はそれぞれの外交目標を「国際社会の目標」の中に組み込んでいかなければならないのです。それでは、最低限の「国際社会の目標」はどのあたりで落ち着くのでしょうか? おそらく、「北朝鮮が国際社会の責任ある一員となること」という言葉に集約されるでしょう。日本をはじめとして、関係国の中で「北朝鮮が国際社会の責任ある一員になること」に反対する国はいないでしょうし、北朝鮮が実際に「国際社会の責任ある一員」になれば、関係国それぞれが抱える問題も解決されていくでしょう。 ただ、現時点では、「国際社会の責任ある一員」という文言が極めてあいまいであることも事実です。このあいまいな言葉の中に具体的な内容を盛り込んでいくことこそ、関係国間の調整であり、いかに自国の目標を組み込めるかが、外交手腕ということになるのです。 それでは、日本にとっての外交目標とは何か、ということになるのですが、それはまさに日本の国民が決めていくことなのだろうと思います。ただ、その際、注意しなければならないのは日本のみならず、米国、韓国、中国など関係国の姿勢も十分考慮しなければならない、ということです。それを前提として、日本にとって何が問題なのかを一人ひとりがしっかりと考え、そのためにはどういう方法が必要なのか、「対話」なのか「圧力」なのか、おのずと答えが出てくるように思います。 また、現在の日本では、北朝鮮についてのさまざまな情報がはんらんしているにもかかわらず、正確な情報が少ないと言わざるを得ません。また、それゆえ、われわれは、そうしたはんらんする情報を取捨選択しなければならないのですが、その判別は極めて難しいと言わざるを得なくなるのです。北朝鮮について真摯(しんし)に知りたいというのであれば、多少、難しいかもしれませんが、次の2冊を推薦します。
1.については、大冊ですが、北朝鮮の歴史を正確に知るための、もっとも良い書籍でしょう。2.は、北朝鮮の政治体制を分析した専門書です。現在の北朝鮮の政治体制の「特異さ」を理解する手がかりとなるでしょう。どちらも分量は多いし、かなり難解だろうと思いますが、北朝鮮を真摯に考えたいという人たちには、ぜひ読んでいただきたい書籍です。これらの書籍を手掛かりとして、北朝鮮についてのさまざまな情報に気を配り、特定の情報だけをもとに判断しないという、バランスの取れた判断をしていただければと思います。 あらためて指摘するまでもなく、北朝鮮の動向は、日本にとって極めて大きな意味を持つでしょうし、北朝鮮問題はそれがどのように処理されていくかにかからず、日本に大きな影響があることは間違いありません。それゆえ、わたしたちは一人ひとりがバランスよく北朝鮮問題の目標とは何なのかを考えなければならないのです。その意味で、半々という結果ではありましたが、「対話」か「圧力」か、を考えることで、何を考えていかなければならないのか、というのが明確にしてもらえたのではないか、と思っております。 | 
静岡県立大学教授 |
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を!![]() 詳細と登録
詳細と登録
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |