
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
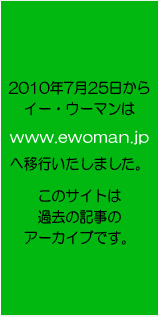 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニマルアシステッドセラピーを実践する際に
皆様のご質問のあまりに核心をついた、本質に触れた、しかも良心的な視点からのご質問に感激しております。すべてのご質問をひとつひとつ抱きしめながらお答えしたいと思います。 あきんぼさん、AAAはかなり一般的になってきていますが、実にさまざまな現場でなされるようになってきています。しかし、それだけに、その現場でおこるであろう、すべての対処は当事者に任されています。ある程度組織だったマニュアルを作成してリスク管理、活動を受け入れる側との同意、折衝、意思確認を行っている団体はそんなに多くはありません。ある意味大変広義に解釈されれば、ティータイムさんが感じられるように、特別な活動でなくても、熱帯魚の水槽をのぞき込むだけでも、同じ空間に動物と共有して眺めているだけでも人の心への効果は実際には「ある」というのが実際のところです。(欧米の歯科医院の一部では熱帯魚の水槽を見ながら処置を受けると使用麻酔量が通常より少ないというデータを持っているそうです)しかし、大切なのは、動物介在のすべての活動(AAA、AAT、AAE)は動物を介して、良い効果をもたらすことであり、そこで「悪い記憶」を残さないことですので、リスク管理(健康面も含めて)は十分に吟味されて行われるべきだと思います。そうしたことを検討しマニュアルをもとに活動している団体は日本ではまだ、多くありません。 そして強調したいのは、AAA、AAT、AAEのそれぞれのプログラムに参加している動物たちは特別なトレーニングで育成された動物たちではなく、一般家庭でおおらかに優しく育てられた普通の家族の一員の犬や猫たちであることです。いま私が最も身近に接しているJAHA(日本動物病院福祉協会)でのこの活動は総称をCAPP(コンパニオンアニマルパートナーシッププログラム)といいます。もちろん適性があるかどうかのテストや認定制度はあります。ですから、ある程度以上の活動に参加するときには認定制度で認定を受けることもあります。(CAPP認定犬や猫と呼ばれます)また、都会では伴侶動物が少ないので難しいのでは?ということも、都会でも今は同居がokの共同住宅も増え、良い伴侶動物を育てておられるご家庭も多くあります。そして、都心の人間の病院でもAATが、(精神科、小児科病棟など)多くの福祉施設でAAAが、そして特に都会の中の小学校などでAAEがすでに始動しています。JAHAによるこの活動は全国組織なのでもちろん東京都心に周辺に限らず、行われています。そしてハンドラーと呼ばれますが、この動物たちにつきそって現場での活動をになう人々の中心は獣医師と獣医看護士そしてもっともメインなのがその伴侶動物のご家族です。そして、Willowさん、すべてはボランティア活動として行われています。ですから、今伴侶動物と暮らしている方で、この記事を読んでもしもそのお気持ちがあって適性があれば、ボランティアスタッフとして参加もできるものなのです。 REIKOさん、参加動物たちの「適性」のお話にふれて下さってとてもうれしいです。このことはとても重要です。参加動物たちはそれぞれ家庭の伴侶動物がメインです。ですから、道具ではありませんし、そのように考えていたらこの活動はうまくいかないと思います。あくまで動物たちには人とふれてもストレスが少ない、またはそうした場に向いている、という適性があることが前提です。その適性は参加の決定の前に専門家により、よく吟味されます。人(ハンドラー)も動物も共に、ボランティアの意志を伝えることからはいり、時には「見学」から入り、少しずつ無理のない、互いに危険のない状況を確認しながら行われていくのです。実際にこの活動に20年以上触れてきましたが、適性のある動物たちの共通の様子として、自分の大好きな家族と共に、家族が望んで出向く社会活動の場で自分たちを介して、人が人に奉仕するというコンセプトがわかっているのかも?と思うほどに、特に活動時間内にはまるでプロが仕事をしているかのような面持ちで活動にのぞんでいることもあります。(←これは私のあくまでフィーリングですが。)また、活動に出かけることにより、動物たちの社会性がのび、活気づくことも少なくありません。そしてハンドラーであり家族である私たち自身も誇りを感じ、社会の中で自分にできる役割、について考える機会を与えてくれます。そして、動物たちのストレスサインはすべてのハンドラーがきちんと学び、日々の体調なども考慮して、動物たちに負担のかからない配慮の中でおこなわれるのです。ですから、どんなに家族が活動に参加したくても動物たちに適性が見いだせなければ参加してはいけないのです。 月の猫さん乗馬療法はまた、非常にすばらしいものですね。大きな動物だけにその動物に騎乗することで視点が変わる、景色が変わる、多くは屋外で良い空気を吸って、という要素もあり、気持ちが晴れ、爽快感もあり、また、大きな馬という動物に自分が騎乗して歩けるという事実が「自信」にもつながるのではないでしょうか? いまいくんさん昨日触れましたが現代社会の子ども達にとっての伴侶動物の存在はおっしゃるとおり、バーチャルでない、リアルの「命」に責任をもつ、接するという意味でも重要だと思います。機会があれば環境が許せばできうる限り、さまざまな側面で動物のみならず、豊かな自然環境の中で植物にも昆虫にも触れながら育って欲しいですね。私も今は都心の中の特に都心の環境におりますが、幼い頃はまだかなり緑豊かな東京のはずれで昆虫、植物(森や林や岩山)、動物たちに囲まれて育ったことに感謝しています。 | 
獣医師 赤坂動物病院副院長 |
|
|
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |