
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
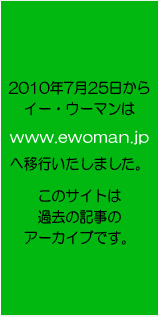 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カジノ合法化への道のりこの話題も、本日が最終日となりました。今までのみなさんからの投稿を読んでみて感じることは、ゲーミングが「文化」として、日本人の生活価値観や生活様式に適合するかどうかを、多くの読者の方々が問題としていたことです。経済効果が大きい点をメリットとして認識しているところは、賛成する方々と反対する方々の双方に共通していたと思います。 ゲーミングはその内容と発展形態から地域性があり、目的や環境も地域によって異なっています。日本では、「緋牡丹お龍」が登場する任侠映画は極端としても、賭博の文化が源流であり、それにパチンコや競輪、競馬等の公営ギャンブルが加わり、庶民的なものとしては宝くじやロトなどが普及しています。 「ゲーミングの伝統も文化もない日本」「カジノ慣れしていない日本人」「日本のギャンブル好きとカジノにギャップ」という指摘がありましたが、その通りだと思います。カードゲームやルーレットなどのゲーミングを通して、社交目的で楽しむことを知らないわたしたちにとっては、いきなりヨーロッパの貴族文化を導入しても、定着は難しいと思われます。ヨーロッパでは、このような形態のゲーミングが「日常」の文化であるのならば、日本に導入する際には、レジャー活動の中で、このような時間の過ごし方も選択できるという程度に考えた方がいいのかもしれません。つまり異文化であることを前提として、それを日本文化に取り入れようとするのではなく、「非日常」的活動として、選択できる環境に位置づけるということです。 またゲーミングの導入に際して、「治安と節度を保つこと」「家庭崩壊の増大」「治安の悪化」も心配される方が多くいらっしゃいました。これらの問題については、諸外国の事例などを研究することによって、ある程度事前に予測できるわけですから、ご指摘にもあったように「解決策を明確にしてから実現すべき」だと考えます。 ゲーミング導入の時期に関しては、1国2制度を用いなくとも、現行法制度の中で、おそらく近い将来に本格導入されると思います。日本政府が地方自治体に対し、以前のように潤沢に交付金を配布できなくなってきたことや、地方活性化の即効薬を模索していること、外国からの観光客受け入れ事業(ウェルカムプラン21など)を促進し、日本の国際化をすすめていく必要があることなどがその根拠です。その場合、いつから、どこに、どのような形で導入していくのかについては、ゲーミングの是非以上に議論を呼びそうですね。おそらくは、現在国会で議論されている「○○特区」の形で導入することが、もっとも軟着陸しやすい形になると思われます。この際、国内にいくつゲーミング施設が必要なのかも大きな問題ですね。東京だけでいくのか、地方も含めて複数にするのか、適切な数に関しては検討が必要です。最初にモデル地区を定めて、行政措置や防犯、効果などに関し、試行錯誤を行いながら、次第に展開する方式となると思います。 ゲーミングを実施段階に落とし込んでいく場合に、もっとも重要なのは経営主体の問題です。「外資企業などの支えがなければ、カジノ自体の運営もうまくいかない」という指摘は、的を得ています。日本企業には、ゲーミング施設経営のノウハウがないわけですから、導入当初は、外資系企業に依存せざるを得ないことと思われます。経営としては、行政が監督して民間が経営する形態となり、中心企業は外国企業という構図になりそうです。こうなると、先ほどの文化の議論のように、異文化を持ち込んで定着化をはかりたい企業と、それを統制する行政、日本向けにリニュアルしたい日本企業との間で、果たしてうまく折り合いがつくのかどうかも疑問です。モデル地域を定めての段階的導入の手法をとることがベターとなります。 導入に際しては、再三指摘されているように、「治安の確保と犯罪の防止」を具体的にどうするのかが最大の課題と思われます。警察や司法の問題ばかりでなく、地域社会として、どのような取り組みが必要となるのかを、事前に検討する必要もありそうです。ゲーミング施設の運営と管理に関しては、オペレーションとマネージメントに関する人材育成が急務です。可能であれば、実際にゲーミング施設を誘致し建設する前に、人材育成のための期間を設け、その人材が育った段階で施設を運営するくらいの余裕を持ったスケジュールが望ましいと思います。これらは、ゲーミングを導入したい自治体が奨学金制度等を活用して留学させたり、専門学校を誘致するなどしてすすめることとなります。 投稿の中ではあまり問題となりませんでしたが、ゲーミング施設周辺の環境形成も重要な問題です。住宅地に隣接して施設をつくるわけにもいきませんし、商業地区の中で展開することも問題です。できれば出入り口を明確にして、その中でゲーミングとその関連施設が運営されるような形態が望ましいと思います。一部の都県では、出島方式も検討されているようですが、これも一考に値します。 みなさんの投稿の中では、ゲーミング施設が単一施設として運営されるイメージで議論されていましたが、実際には複合施設化が望ましいと考えます。関連機能としては、コンベンション機能、エンターテイメント機能、飲食機能、宿泊機能、交通結節点化することによるターミナル機能、情報センター機能、ショッピング機能などが考えられます。よく知られるラスベガスは、ゲーミングと宿泊施設を一体化した上で、エンターテイメント機能の充実を行い、次にコンベンション機能の充実に腐心してきました。最近ではIT技術を集約して、デジタルシティーという未来都市のコンセプトも提案されています。また周辺地域での別荘開発なども盛んで、単にゲーミングに埋没するだけの都市でなく、住環境、リゾート環境としての充実をめざしているようです。 今後このような議論をさらに深めていくためには、それぞれの人の経験によって自由に描かれるイメージに基づいた議論ではなく、具体的な構想をたたき台として、何が問題であるのかを見つけ出すことから始めることが適当だと思います。次に、抽出された課題が、現段階で解決可能であるのかどうかの検証を行うことです。この段階で解決不可能な課題があれば、その時、この計画を断念するのか延期するのか、実施に移行しながら解決策を模索するのか、判断することになります。 中央政府にも関連省庁の間で連絡協議会などの設置が必要でしょうし、地元では提案された原案を元に研究する体制が求められます。ゲーミングは、まさに文化の問題ですから、慎重に議論を進めることにしくはないと思います。 この数日間をみなさんとともに考え、ゲーミング問題の奥の深さを感じました。また投稿なさる方の意識とレベルの高さに改めて感嘆いたしました。このような、日常のふとした疑問を、集中的に扱うeWomanのみなさんのセンスの良さも光っていますね。また何かの話題でお目にかかれれば幸いです。投稿していただいたみなさんに深く感謝いたします。 | 
名桜大学教授 |
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を!![]() 詳細と登録
詳細と登録
現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |