
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
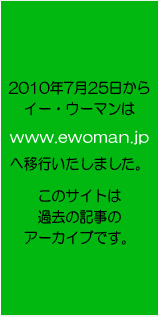 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折にふれて見直すことも必要
生命保険に加入なさっている方、なさっていない方、いろんなご意見が寄せられましたが、それぞれにしっかり考えていらっしゃるようで、とても頼もしく思います。ただ、しっかり考えたつもりだったけれど盲点があったということもありますし、家族構成の変化などで必要な保障が変わったりしますから、折にふれての見直しが大切ですね。あ、それから、ひとつ気になったのは「保険金を払う」という言葉。私たちが保険会社に払うのは「保険料」で、「保険金」は保険事故があったときに保険会社が払ってくれるお金です。ちょっとしたことですけど、この違いも知っておきましょうね。 「今死んだら親の老後の面倒がみれなくなる」と実感して保険に加入なさったドラゴンさん。ほんとうに親孝行なんですね。一般的にいって、女性にはそれほど高額な死亡保障は不要ですが、共働きで家計を担っている方、家族の扶養義務がある方、高齢な家族や障害のある家族がいる方などは、死亡保障の保険にも加入しておいたほうがいいと思います。私も子どもの扶養義務があったし、会社を経営していたので、それなりの保険に加入していました。子どもが成人し、会社も縮小したので、減額しようかなと思っていた矢先に病気になり、視力障害の不安が出てきたため、自分の後遺障害の保障としてそのまま残しています。たしかに保険は「何もなければもったいない」、でも何かあったときのために、最低限の保障は準備しておいたほうがいいですね。 2人目のお子さん出産を機に見直しを考えていらっしゃるkotan87さん。保険も自由化時代になり、数多くの保険会社や共済機関から新商品がどんどん発売されています。しっかり比較検討してベストの商品を選んでくださいね。 ゆかりっくすさんは死亡保障額をいくらにするか、迷っていらっしゃるようですね。必要保障額は、(1)夫死亡後の支出(家族の生活費、子どもの教育費、住居費、不時の出費、夫の葬式代、車ローンなどの借金があれば、その精算分)を計算し、一方で、(2)夫死亡後の収入(公的年金からおりる遺族年金、妻の収入、貯蓄など)を計算して差し引きします。(1)−(2)がマイナスであれば、それが必要保障額というわけです。ゆかりっくすさんの場合、ご主人がサラリーマンか公務員であれば、遺族年金もそれなりの額がありますし、ゆかりっくすさんにも収入があるので、家族の生活費はそれでまかなえるでしょう。住居費のほうは、マイホームを購入済みであれば住宅ローンを組んでいても不要、賃貸や社宅などに住んでいらっしゃるなら2,000万円程度。お子さんの教育費はひとり1,000万円程度。不時の出費と葬式代として1,000万円程度。つまり、マイホームを購入済みなら死亡保障額は2,000万円、購入前なら4,000万円くらいあればよいのではないでしょうか。 かえるんるんさんのお義母様の保険は、なかなか難しいですね。たしかに60代でも、既往症があっても加入できる保険はあるのですが、それらの保険には免責がついています。加入はできるけれど、既往症に関係ある病気で入院したり手術を受けても保険金や給付金は支払われません。ことにリウマチは全身への影響が大きいため、かなり難しい病気。加入に際しては、セールスレディや代理店としっかり相談して、どんなときに支払われるか、どんなときは支払われないかを確認してください。お義母様の場合は、貯蓄で準備したほうがよいのではないかと思います。 「万一の時には貯蓄から捻出すればよい」と考えていらっしゃるNSさん。その考え方も正解です。昨日のコメントにも書きましたが、万一のときの支出を貯蓄でまかなえるなら、保険は不要です。保険料分を貯めていけば、さらに貯蓄を増やせますしね。ただ、生計の担い手である夫の死亡、自動車事故、火事や地震などで大きな出費があったときは、貯蓄だけではまかないきれないため、保険が必要になってきます。この際、いろんなケースを想定し、必要額を計算してみて、保険に加入するかしないかを考えてみられるといいですね。 Emeraldさんの投稿には、生命保険と損害保険の違い、火災保険と地震保険の違い、社会保障と生命保険の関係、医療保険と代替医学など、さまざまな問題が含まれています。ここですべてにコメントすることはできませんので、医療保険と代替医学について考えてみましょう。現在の医療保険は、病気やケガで入院したときのみ給付金が支払われるものが主流で、在宅療養や代替医学は対象になっていません。一方、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアなどは「実損填補型」といって、実際に自己負担した費用分が支払われる医療保険が主流です。今後は日本でもこのタイプが登場してくると思いますが、その場合でも、公的医療保険の自己負担分は補填されても、代替医学の負担分まで補填されるかどうかは疑問です。私の場合、入院して公的医療保険対象の西洋治療を受け、この分に対しては給付金が支払われました。現在は在宅で代替医学も受けていますが、この分にはいっさい給付金が支払われません。だからといって保険が役に立たなかったというと、けっしてそんなことはない。やはり保険と貯蓄の両方が必要だと痛感しています。このあたりの兼ね合いを検討して、保険に加入するかどうかを決められてはいかがでしょう。 | 
家計の見直し相談センター |
|
|
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |