
 |
|サイトマップ|お問い合わせ| |
|
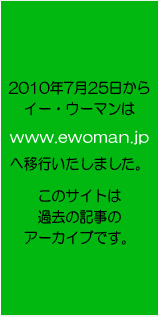 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彼らと共に暮らすために
毎日の心震えるご投稿に心から感謝します。YesよりNoが多いにも関わらず、たくさんの方が関心を傾けてくださったことに感激です。 kasamiさん、うちの病院にも、ご家族の名字に動物の名前を記入する診察ノートがあり、毎回、記録が重ねられていきます。外で患者さん(のご家族)にお会いすると「まあ! ○○ちゃんのママ! こんにちは」という会話が交わされることもあります。 miechanさん、わたしも昨年17歳の猫を母と共に見送りました。彼の骨を拾いましたが,供養の方法は家庭と遺族のその時の気持ちにあった方法で行われるのが良いと思います。何より、のほっちさんもおっしゃるように、生きている間、十分に看て「精一杯」を尽くしてお別れをし、彼らのくれた愛情の種を元に、人や動物や環境への愛情を深めて、元気に生きていくことが大切だと感じます。 もるちゃんさんが触れておられるけれど、伴侶動物と暮らす前に考えることがたくさんあります。どういう動物と暮らすのが一番良いのか? 本当は暮らせないのか? どういう環境で、どんな経済計画で、どういう家族構成で? 生涯に必要な予防・治療・医療保険は? 主治医は? しつけは? もしも自分が先に逝ったら……? 生きている以上、計画通りには行かないこと(ばかりかも)もありますが、十分に考え、ある程度の決意と覚悟が必要です。その相談は、主治医探しと共に動物病院に尋ねる、獣医看護士やしつけのインストラクターなどの専門家に尋ねるなどケースも増えてきました。 これからの課題もたくさんあります。 独居の高齢者が年齢を考えると伴侶動物と暮らせないと思ってしまう。でも本当はその時期にこそ、一番必要な温かさを与えてくれる存在です。 家族が先に逝った場合や、社会で役割を担って働いている犬たちの老後の受け皿となるシステム、捨てられたり屋外で繁殖した結果、保護された動物の家族探し、遺伝疾患のない健やかな子犬を誕生させるシステムなどについて考えることは、今後の課題です。 そして、伴侶動物医療に、できる限り家族が一緒に臨み参加し理解し、医療現場と手を携えていけるようにしていくことも大事です。枝利子さんが思うような自由な生活を犬たちに与えられるとしたら、やはり広い地所が必要です。不妊手術も必要でしょう。伝染病、動物嫌いな人との関係……あらゆる環境を変えたのは人間なのですから、DEYOKOさんのような出会い方をして、被害を受けてしまうことがないように、伴侶動物と暮らす人間としての自覚を持っていたいですね。wakanoさんがまたいつか伴侶動物と出会うときには、より良い出会いであってほしい!と願ってやみません。 伴侶動物と関わることは、地球全体を考える糸口だと思うときがあります。伴侶動物と一緒に暮らすのはなぜか? 一緒に暮らす前に知っておくべきこと、共に「すばらしい」暮らし、お別れのこと、お別れのその後まで、すべてのステージで関わることであり、わたしたち自身のことを深く考えるきっかけにもなるような気がします。 | 
獣医師 赤坂動物病院副院長 |
|
|
|
|
|
| ©2000-2009 ewoman,Inc. | |個人情報について|利用規約|各種お問い合わせ・お申し込み|会社概要| |